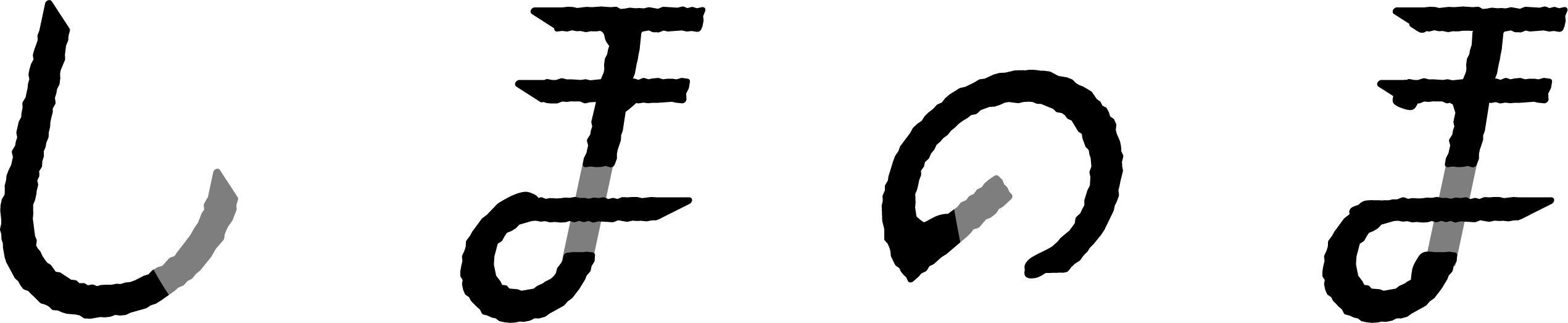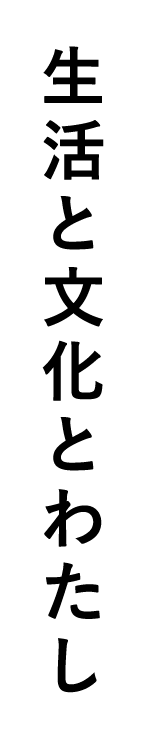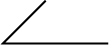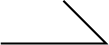奄美大島で盛んに栽培されているさとうきび。前回(【さとうきびを巡る島の話 第1話】)も触れたように、内部に甘い液体を含む繊維が詰まっている竹のようなものだ。
奄美の特産である黒糖焼酎や、長寿を支える「キビ酢」、そしてお茶請けとして昔から食されてきた黒糖はさとうきびを原料とし、島民にとっては無くてはならない存在。
ミネラルを多く含み、栄養価の高い健康食品として島外からも注目を集めている。
竹のような節のある茎を持つさとうきびからどのようにして黒糖が作られるのだろうか?
今回は、奄美大島の笠利町で黒糖を作っている肥後農園の肥後 安美(ひご やすみ)さんを訪ねた。
シンプルながらも手間のかかる黒糖づくり
肥後さんは自身が小さいころから慣れ親しんだ昔ながらの製法にこだわり、黒糖づくりを行なっている。奄美では砂糖のことを「サタ」と言い、黒糖の事をこう呼んでいる。
まずは畑からさとうきびを手で刈ってくる。機械で刈ってしまうと絞りの工程ができないし、草なども混じってしまう。肥後さんはさとうきび農家でもあるので、黒糖の材料はすべて自分の畑のさとうきびなのだそうだ。

さとうきびは内部の繊維質の部分に甘い汁がたくさん含まれているので、これを圧搾機で搾る。機械に茎を真っ直ぐに入れていくと、中からジュワっとさとうきびの汁が流れ出てくる。
このさとうきびの汁は、草のようなフレッシュな香りのする甘いジュースだ。味は甘いアイスグリーンティーに似ていて、そのまま飲んでもおいしい。

この汁を網と漉し布を使って漉してから、平たく四角い釜に入れ、煮詰めていく。
黒糖を固めるためと不純物を取り除くために、少量の食品用石灰を入れ、灰汁を丁寧に取りながら煮詰める。
1kgのさとうきびから取れるさとうきび汁は約500g。それを煮詰めて黒糖にすると約100gになる。畑から刈ったさとうきびのなんと1/10しか黒糖は取れないのだ。
そこまで煮詰めるのにじっくりとかき回し続けながら、約3時間も煮詰める。

「サタづくりで一番難しいのは、やっぱり石灰の量と温度管理かな。」
と、肥後さんは丁寧に温度を見ながら火加減を細かく調整する。
「今日のキビ(さとうきび)は太茎種という昔からある種類のキビ。これは焦げやすいからね。気を付けないと。」
そう言いながら、手を止めることなく木の棒で丁寧に混ぜながら、均一に火を通していく肥後さん。

最初は水のようにさらさらとした液体だったのが、だんだんと茶色くなってきて粘り気も出始めてきた。この状態までくるとここからは時間との勝負だ。
この段階の黒糖は、トロトロに溶けた水あめのような状態だ。
ひしゃくですくいながら、一気に撹拌機(かくはんき)に移す。液体状の黒糖は温度が下がるとともにどんどん固まってしまうので、大急ぎで行う。

移し終わったら、撹拌機を回して空気を含ませて攪拌する。これにより、黒糖が冷えて結晶化し、固まりやすくなる。攪拌して滑らかになったら、トレイに流し込み、薄く広げて冷ましていく。
この攪拌した、まだ温かい状態の黒糖が私は大好きだ。和菓子の餡子のような柔らかさで、黒糖の香りが強い。

黒糖が完全に固まる前に切り込みを入れ、あとでカットしやすいようにする。

冷えて固まったら、細かくはさみでカットすると黒糖が完成する。

「黒糖は作るたびに味が違う。同じ品種のさとうきびでも、畑によって味が違うのだよ。作ってみないとどんな味に仕上がるかわからない。そこがまた面白いところだね。」と語る肥後さん。
今日の黒糖はどんな味に仕上がったか、食べるのが楽しみだ。

黒糖作りの歴史をさかのぼる
文献から黒糖づくりの歴史をさかのぼると、第1話で触れたように、直 川智(すなお かわち)が中国からさとうきびの苗を持ち帰り、奄美大島の大和村で栽培したことに行きあたる。そのときに製糖技術も持ち帰ったということだ。
その後、製糖方法も島に合わせて徐々に改良され、文献として確認できる江戸時代の製糖の様子は名越左源太(なごや さげんた)が奄美の様子を書き記した「南島雑話(なんとうざつわ)」に残されている。

奄美博物館蔵:南島雑話より
円筒型のローラーでさとうきびを挟んで圧搾する機械が作られ(転子型圧搾機)、馬や牛に引っ張らせて円筒を回して圧搾し、釜で煮詰めている様子が描かれている。
さとうきびは栽培から製糖まで、このように労力のかかる工程が多かったため、プランテーション式の共同作業で行なわれていたらしい。
このころの奄美は既に国内でも屈指の製糖技術を持ち、種子島や琉球などにその技術を伝えていたほどだったそうだ。
集落の共同作業による黒糖づくり
近代でも、島内に大規模な製糖工場ができるまでは、農家が共同で黒糖を作って出荷していた。
肥後さんの住む万屋(まんや)集落にはさとうきび農家が多く、集落所有の2軒のサタ小屋(製糖工場)があったので、農家は2つのグループに分かれ、それぞれのサタ小屋で共同作業によりさとうきびを一軒分ずつ製糖していたのだという。

肥後 安美さん
しかし、1963年に笠利町に富国製糖の製糖工場ができて、集落の農家は製糖工場にさとうきびを出荷するようになった。そのため、集落のサタ小屋は使われなくなったということだ。
肥後さんの家は昔からさとうきびの栽培農家だったので、肥後さんは子どもの頃、集落のサタ小屋での黒糖づくりをいつも見ていた。
製糖工場のおかげで農家の作業が楽になった半面、昔ながらのサタ小屋で黒糖づくりをするところがほとんどなくなってしまった。
そのため肥後さんはそのサタ小屋での伝統的な黒糖づくりをいつかは復活させたいとずっと思っていて、ようやく夢が叶ったのが今の「肥後農園」だと話してくれた。
島人の暮らしに根付いている黒糖
このようにして作った黒糖は、島ではお茶請けとして、お菓子のように食べる。
黒糖はさとうきびの搾り汁を全く精製せずに煮詰めて固めたものだ。さとうきびに含まれるミネラルが凝縮され、栄養価がとても高く、深いコクと甘く強い香りがあるのが特徴だ。

島を初めて訪れた人は「砂糖の塊をそのまま食べるの?」とびっくりするが、ポリポリと塊のまま食べることにより、黒糖の香りとコクが味わえるのだ。
島では黒糖はとても身近な食べ物で、知人の家などを訪問したとき、お茶と一緒に黒糖が出されるのは日常茶飯事だ。コーヒーや紅茶に黒糖を入れる人もいる。
黒糖を粉末にしたものは、ウワンフネ(豚の塊肉と野菜の煮物)、豚の角煮、豚骨など深みのある味を出したい島料理には必ず使われる。
島料理以外にも「煮物には黒糖を使う」という人は多く、島の家庭に黒糖が常備されているのもよく見る光景だ。

豚骨の煮物
島の昔ながらの手作りのお菓子にも黒糖は必需品。ふくれ菓子(蒸しケーキ)・ごまざた・かりんとう・かしゃ餅・ふなやき・黒糖豆など、黒糖の風味を活かしたものが多い。

黒糖を使ったかしゃ餅

黒糖を使ったふくれ菓子
高度成長期に入るまで、白砂糖はとても貴重で島にはあまりなかったということもあり、一般家庭では料理に使う砂糖はほぼ黒糖だった。しかし生産地とはいえ、黒糖も作るのに非常に手間がかかり、高価なものだったので、少しずつ大事に使っていたそうだ。
また、黒糖を「クスリザタ(薬砂糖)」と呼んで、農作業などで疲れたときや体調が悪いときに、栄養剤のように少しずつ食べたりしていたと聞く。
このように昔から島の人の生活にとって、なくてはならないものだった黒糖は、今でも必需品だ。
黒糖づくりを見学することもできる
今回訪れた肥後農園の純黒糖は、製糖工場に直接行って買うことも可能。
黒糖の製造時期は限られるが、冬~春にかけての時期は、タイミングが合えば、製糖しているところを見学することができる。

肥後農園
ただし、煮詰めている黒糖は高温なので、近寄ったり触ったりすると危険だ。くれぐれも十分に注意し、作業の邪魔をしないようにして見学しよう。
今回は、さとうきびからどのようにして黒糖が作られるのか、昔ながらの黒糖づくりについて取材した。次回はこの黒糖を使って作られる黒糖焼酎について、蔵見学をしながらお話を伺う。どうぞお楽しみに。
肥後農園(肥後 安美)
所在地:〒894-0502 鹿児島県奄美市笠利町万屋988-1
TEL:090-7462-1231
FAX:0997-63-2009